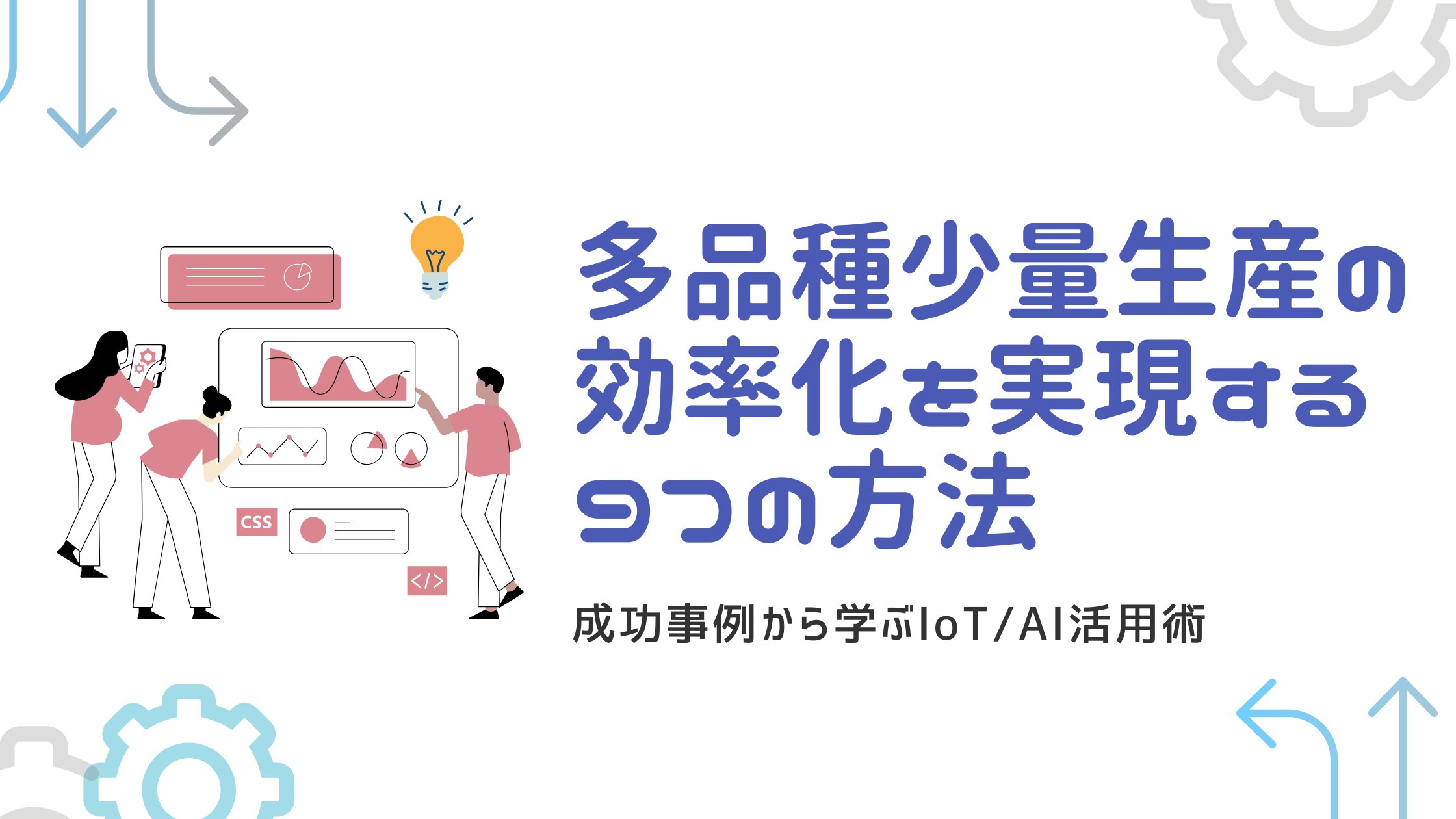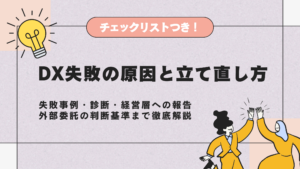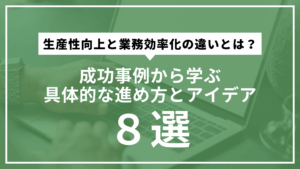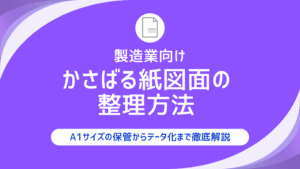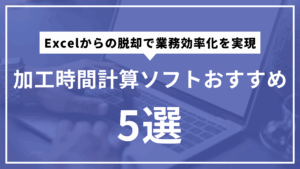「また段取り替えでラインが止まる…生産性が全然上がらない」



「品種が多すぎて、在庫や部品の管理がもう限界だ」



「ベテランの勘頼みの生産計画や見積もりから抜け出したい」



「この製品は本当に儲かっているのか原価が曖昧だ」
多様化する顧客ニーズに応えるため、『多品種少量生産』は多くの製造業にとって避けては通れない道です。
しかしその裏側で、頻繁な段取り替えによる生産性の低下、コストの増大、複雑化する管理業務に頭を悩ませている経営者や現場責任者の方は非常に多いのではないでしょうか。
「顧客の要求には応えたい、でも利益が出ない…」
そんなジレンマを解消し、多品種少量生産を“儲かる仕組み”に変えるには、正しい手順での効率化が不可欠です。
本記事では、多くの企業が直面する多品種少量生産の課題を6つに整理し、明日からでも実践できる9つの具体的な効率化アプローチを徹底解説します。
現場の地道な改善活動から、生産管理システムの選び方、さらにはAIやIoTといった最新テクノロジーの活用法、そして実際に効率化を成功させた企業の事例まで、網羅的にご紹介します。
- 自社が抱える課題の根本原因が明確になる
- コストをかけずに始められる具体的な改善策がわかる
- 多品種少量生産の生産性を向上させコスト削減を実現するための道筋が見える
- AIなどの最新技術を自社にどう活かせるか具体的なイメージが湧く
なぜ今、多品種少量生産の「効率化」が急務なのか?
「必要なものを、必要なときに、必要なだけ作る」という多品種少量生産。この言葉自体は新しいものではありませんが、近年、その「効率化」が企業の存続を左右するほど重要な経営課題となっています。その背景には、大きく3つの時代の変化があります。
顧客ニーズの多様化と短サイクル化
現代の消費者は、単に機能的な満足を求めるだけではありません。「自分だけの特別なものが欲しい」「人とは違う個性を表現したい」といった、パーソナライズされた製品への要求が高まっています。これにより、製品のライフサイクルは短くなり、企業は次々と新しいバリエーションの製品を生み出し続ける必要に迫られています。
インダストリー4.0とマス・カスタマイゼーションの波
IoTやAIといったデジタル技術の進化は、「インダストリー4.0」と呼ばれる新しい産業革命を引き起こしました。これにより、「マス・カスタマイゼーション」、つまり一人ひとりの細かい要求に応える製品を、大量生産品に近いコストで提供することが現実的な目標となっています。この潮流に乗り遅れることは、大きなビジネスチャンスの喪失を意味します。
放置するリスク
こうした変化のなかで、旧来の生産方式のまま非効率な多品種少量生産を続けているとどうなるでしょうか。答えは明確です。頻繁な段取り替えによる稼働率の低下、管理コストの増大、納期の遅延などが積み重なり、収益性は悪化の一途をたどります。気づいたときには、効率化を達成した競合他社に価格でも納期でも太刀打ちできなくなっている…そんな事態に陥りかねないのです。
多品種少量生産が抱える、6つの代表的な課題
効率化の必要性は分かっていても、何から手をつければ良いのかわからない。そう感じる方も多いでしょう。まずは、多くの製造現場で共通して聞かれる「あるある」な課題を6つ整理し、自社の状況と照らし合わせてみましょう。
- 生産性の低下
製品Aから製品Bへ切り替えるたびに発生する「段取り替え」。この作業中は生産ラインが完全に停止するため、その時間が長引くほど全体の生産性は低下します。品種が増えれば増えるほど、この「ラインが止まっている時間」が経営を圧迫する最大のボトルネックとなりがちです。 - コストの増加
少量ずつ生産するため原材料のロットが小さくなり仕入れコストが割高になります。また、様々な製品の製造に対応できる「多能工」の育成も不可欠ですが、そのための教育や訓練にも相応の時間とコストがかかります。 - 生産計画の複雑化
どの製品を、いつ、どのラインで、どの順番で生産すれば最も効率が良いのか、品種、納期、使用設備、人員スキルといった無数の要素が絡み合うため最適な生産計画を人の手で立案するのは至難の業です。結果として経験と勘に頼った非効率な計画になりがちです。 - 品質の管理の難しさ
作る製品が頻繁に変わるため作業手順の標準化が追いつきません。作業員の習熟度にもばらつきが出やすく、ヒューマンエラーによる不良品の発生や製品ごとの品質のばらつきが起こりやすい環境と言えます。 - 在庫管理の煩雑さ
扱う部品や材料の種類が爆発的に増加。さらに、製造途中の「仕掛品」や完成した製品の在庫も多岐にわたるため管理が非常に煩雑になります。正確な在庫数を把握できず、過剰在庫によるキャッシュフローの悪化や欠品による生産停止リスクを常に抱えることになります。 - 正確な原価把握の困難さ
製品ごとに材料費や加工時間が異なるため、一つひとつの製品の正確な原価を計算するのが非常に困難です。結果として「どんぶり勘定」になりやすく、「儲かっていると思っていた製品が実は赤字だった」といった事態も珍しくありません。
【明日からできる】多品種少量生産を効率化する9つの具体策
自社の課題が見えてきたら、次はいよいよ具体的な解決策です。ここでは、明日からでも取り組める改善策を「現状分析」「現場改善」「テクノロジー活用」の3ステップ、合計9つの方法に分けてご紹介します。
【ステップ1】現状分析と戦略立案
いきなり現場の改善に手をつける前に、まずは自社の生産状況を正しく把握し戦略を立てることが成功への近道です。
受注パターンの分析
すべての製品を同じように管理していませんか?横軸に「ロットサイズ(1回の生産量)」、縦軸に「受注頻度」をとったマトリクスに自社製品をプロットしてみましょう。すると、「頻繁に大ロットで受注するもの」から「たまに小ロットで受注するもの」まで、4つのグループに分類できるはずです。これにより、「どの製品は見込みで生産して在庫を持っておくべきか」「どの製品は完全受注生産にすべきか」といった、製品ごとの最適な生産方式が見えてきます。
部品の共通化・標準化
設計段階にまで遡って、異なる製品間で使える部品を共通化・標準化できないか検討しましょう。使用する部品の種類を減らすことができれば、発注・在庫管理の手間が大幅に削減され、段取り替えの時間も短縮できます。レゴブロックのように、基本的な「ベースパーツ」をある程度見込み生産しておき、受注後に最終的なカスタマイズだけを行うというアプローチも非常に有効です。
【ステップ2】現場の改善活動
戦略が定まったら、いよいよ生産現場の改善に着手します。コストをかけずに大きな効果が期待できる活動も数多くあります。
「段取り替え」の徹底的な効率化
段取り替えの作業内容を洗い出し、「ラインを止めないとできない作業(内段取り)」と「ラインを動かしながらでも準備できる作業(外段取り)」に分けましょう。そして、外段取りの比率を極限まで高めるのです。例えば、次の生産で使う金型や治具、材料をあらかじめキット化して準備しておくことで、ラインの停止時間を最小限に抑えることができます。
生産ラインのレイアウト見直し
作業員の動線や部品の運搬経路に「ムダ」はありませんか?モノを探す時間、遠くまで取りに行く時間は、すべてコストです。使用頻度の高い工具や部品を作業者の手元に配置したり、工程順に設備を並べ替えたりと、レイアウトを最適化するだけで生産性は劇的に向上します。
作業員の多能工化と標準化
多能工の育成は不可欠ですが、OJTだけに頼ると教育に時間がかかり、品質も安定しません。そこで、作業手順書をデジタル化してモニターに表示したり、最新技術である「プロジェクションマッピング」を活用したりするのが有効です。作業台に必要な部品の位置や組み立て手順を光で直接映し出すことで、新人でもミスなく、ベテランに近いスピードで作業を進めることが可能になります。
【ステップ3】システムとテクノロジーの活用
現場の改善活動と並行して、システムやテクノロジーの力を借りることで、効率化はさらに加速します。
在庫管理の適正化
無数にある在庫をすべて同じように管理するのは非効率です。そこで有効なのが「ABC分析」。在庫品目を「重要度が非常に高いAグループ」「中程度のBグループ」「低いCグループ」に分け、管理の優先順位をつける手法です。Aグループは重点的に管理して欠品を防ぎ、Cグループは管理の手間を省くなど、メリハリをつけることで、在庫の全体最適化が図れます。
「生産の見える化」
「今、どの製品が、どの工程にあって、進捗はどれくらいか」この情報がリアルタイムで共有できていますか?難しく考える必要はありません。まずは共有のExcelやスプレッドシートに実績を入力することからでも「見える化」は始められます。情報共有がスムーズになるだけで、手戻りや確認の手間が大幅に削減されます。
生産管理システムの導入
Excelでの管理に限界を感じたら、生産管理システムの導入を検討しましょう。受注から生産、出荷、在庫、原価まで、製造に関するあらゆる情報を一元管理できるため、部門間の連携がスムーズになり、生産計画の精度も向上します。近年は中小企業向けに低コストで導入できるクラウド型のシステムも増えています。
AI・IoTの活用
さらに一歩進んだ効率化を目指すならAIやIoTの活用が鍵となります。例えば、製品の完成後に人の目で行っていた検査をAIによる画像認識で自動化する。あるいは、各設備にIoTセンサーを取り付けて稼働データを収集・分析し、AIが最適な生産スケジュールを立案するなど、これまで人の経験と勘に頼っていた領域をテクノロジーで代替・高度化することが可能です。
【成功事例】あの企業はこうして効率化を実現した!
実際に企業がどのようにして効率化を達成したのか具体的な事例を見ていきましょう。自社で取り組む際のイメージがより鮮明になるはずです。
- 飲料メーカーの事例:生産スケジューラ導入で計画工数を63%削減
ある大手飲料メーカーでは、多岐にわたる製品の生産計画立案に担当者が数日がかりで取り組んでいました。そこで、AIが最適な生産順序を計算する「生産スケジューラ」を導入。結果、計画立案にかかる工数を63%も削減できただけでなく、製品の切り替えに伴う洗浄などの段取り回数も大幅に減らすことに成功し生産性向上に大きく貢献しました。 - 町工場の事例:脱・紙ベース管理で情報共有を円滑化
従業員10数名の町工場では、ベテラン職人の頭の中にしか無い情報が多く紙の指示書による管理で事務所と工場の連携がうまくいかないという課題を抱えていました。そこで、高価なシステムの導入ではなく、まずはExcelで部品表や顧客情報をデータベース化することからスタート。徐々に進捗管理などもデジタル化していくことで、誰でもリアルタイムに状況を把握できるようになり、確認の手間や伝達ミスが劇的に減少しました。
樹脂精密加工会社の事例:「AI見積もり」で見積もり時間を劇的に短縮し、受注率が10%向上!
樹脂精密加工を手がける株式会社プラポート様では、多品種少量生産の宿命ともいえる「見積もり業務の負荷」に大きな課題を抱えていました。
- 導入前の課題
- 日々大量に舞い込む見積もり依頼に対し、営業担当者が図面を見ながら手動で計算。ベテランの経験と勘に頼るため膨大な時間がかかっていた。
- 見積もり回答に時間がかかりすぎるため、顧客を待たせてしまい受注率が30%程度に留まっていた。
- 本来注力すべき他の営業活動や顧客フォローに時間を割けず多くのビジネスチャンスを逸していた。
- 解決策と導入後の成果
- そこで同社は、「SellBOT」を導入。
- これまで数時間〜1日かかっていた見積もり回答が、最短わずか10分に短縮。
- この圧倒的なスピード対応が顧客に評価され、受注率は30%から約40%へと10%も向上しました。
- 担当者からは「導入効果は絶大で今ではSellBOTのない業務は考えられない」との声が上がっており、業務効率化によって従業員の退社時間も早くなるなど働き方改革にも繋がっています。
まとめ|次のステップは「AIによる自動化」です
多品種少量生産の効率化を実現するための9つの具体的な方法を3つのステップに分けて解説してきました。
- 課題の明確化:まずは自社が抱える6つの課題のどれに当てはまるのかを認識する。
- 段階的な改善:「現状分析」から始め、「現場改善」、そして「システム活用」へと、多様な打ち手を組み合わせて段階的に進めることが成功のカギ。
これらのアプローチは、生産性を高めコストを削減する上で非常に有効です。
しかし、人手不足がますます深刻化し、顧客の要求がさらに高度化する未来を見据えたとき、これらの改善努力だけでは限界が訪れるかもしれません。
そこで、次なる一手として避けては通れないのが、「AIによる業務の自動化」です。生産現場だけでなく、これまで人が時間をかけて行ってきた間接業務にこそAI活用の大きなポテンシャルが眠っています。
「図面検索」「見積もり」「データ入力」の自動化で、さらなる効率化へ
製造業では、生産現場だけでなく、過去の図面探し、見積もり作成、図面情報のシステム入力といった間接業務にも多くの時間が割かれ生産性を阻害する大きな要因となっています。
弊社のAIサービス「SellBOT」は、これらの非効率な業務を自動化するための強力なツールです。
類似図面AI検索
探している図面に類似した過去図面をAIが瞬時に検索。さらに図面間の「差分」もハイライト表示するため、流用設計や過去案件の参照が劇的にスピードアップします。ベテランの頭の中にしかなかった「あの図面」を、誰もが1分で見つけ出せます。
AI見積もり
2D図面をアップロード後に、AIがわずか数秒で材料費と加工費を計算。ベテランの経験と勘に頼っていた見積もり作業を標準化し属人化を解消。迅速かつ精度の高い見積もりでビジネスチャンスを逃しません。
AIテキスト抽出・解析
PDFやTIFFの図面から、図番・品名・数量などの文字情報や記号をAIが自動で読み取りデータ化。これまで5分かかっていた手入力作業がわずか5秒で完了し入力ミスも撲滅します。
よくある質問(Q&A)
最後に、多品種少量生産の効率化に関するよくある質問にお答えします。