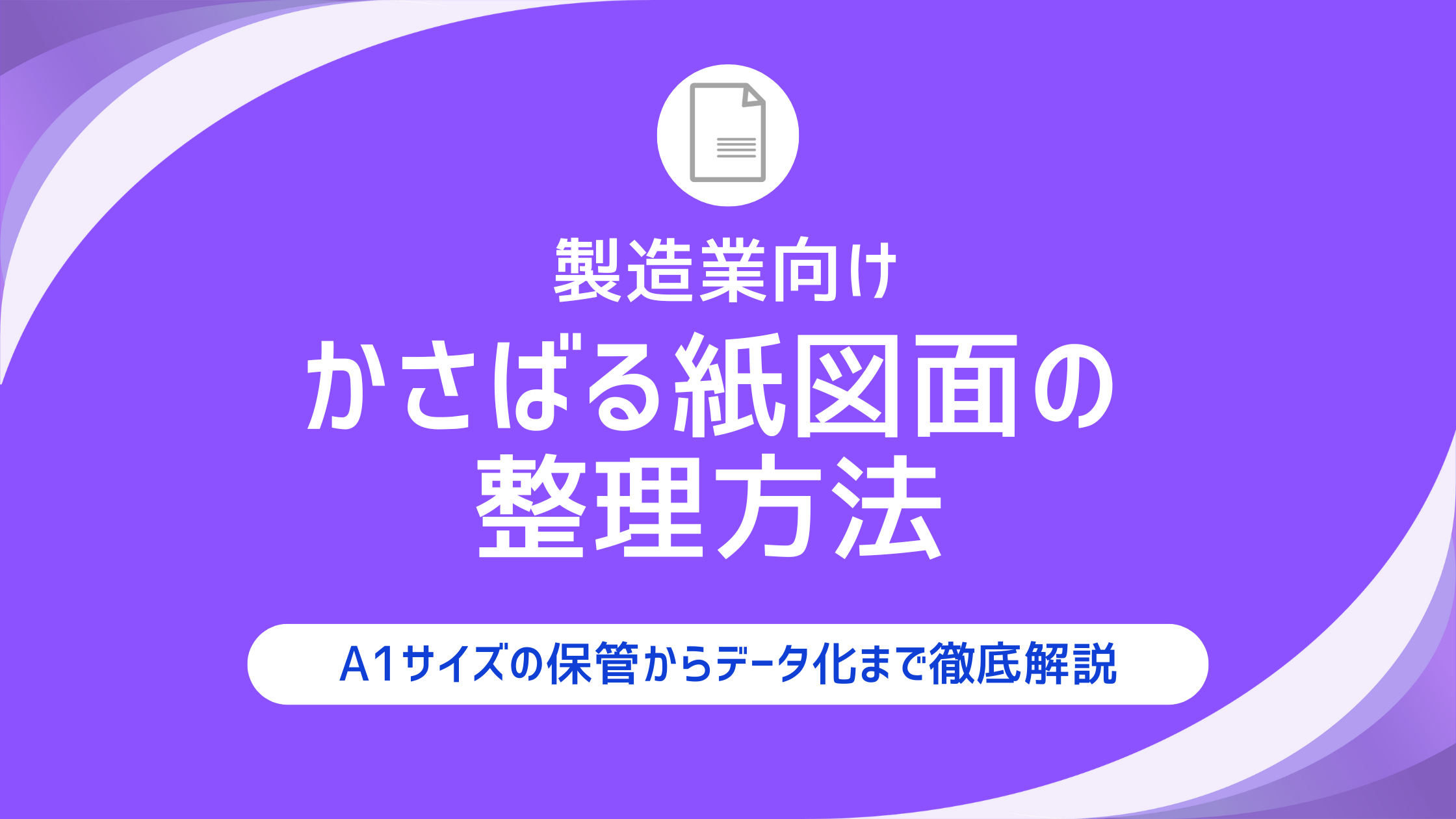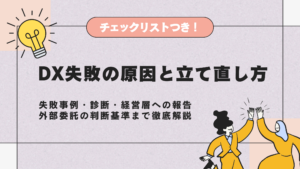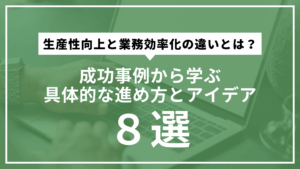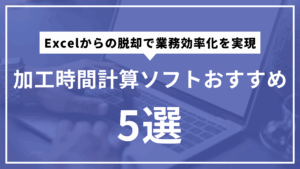「必要な図面がすぐに見つからない…」
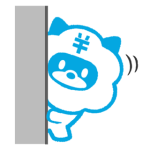
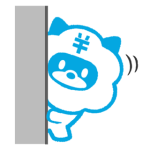
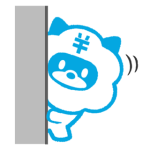
「A1サイズの図面がかさばって保管スペースを圧迫している…」



「紙図面の廃棄方法がわからない…」
こんな悩みに答えます!
製造業の現場では日々増え続ける紙図面の管理に悩まされますよね。図面は会社の重要な資産ですがその管理方法は属人化しがちで担当者にとっては大きな負担です。
紙図面の管理をこのまま続けていては探す時間という見えないコストが発生し続けるだけでなく、紛失や劣化のリスクも避けられません。こうした課題は企業の生産性を大きく左右する重要な問題と言えるでしょう。
そこでこの記事では、今すぐできる紙図面の具体的な整理・保管方法をご紹介します。
また、課題を根本から解決するデータ化の手順も解説します。
本記事を参考に図面を探す無駄な時間をなくし生産性を向上させる一歩を踏み出しましょう。
【この記事でわかること】
- かさばる紙図面は「仕分け」「ルール化」「台帳作成」の3ステップで整理
- 紙管理の課題は検索性や共有性に優れた「データ化」で根本から解決できる
- 図面管理システムを導入することで生産性向上が実現する
なぜ紙の図面管理は大変なのか?紙図面で管理するメリット・デメリットを改めて振り返る
長年慣れ親しんだ紙での図面管理。まずはそのメリットと現場を悩ませるデメリットを改めて振り返り課題を明確にしましょう。
紙図面で管理するメリット
紙の図面には直感的に扱えるというメリットがあります。
- 一覧性が高い: 大きな机に広げれば複数の図面を一度に見比べることができる。
- 書き込みが容易: 赤ペンで修正指示を書き込んだり付箋を貼ったりと誰でも手軽に情報を追記できる
- ITスキルが不要: パソコン操作が苦手な社員でも扱いやすい
- 電源やネット環境が不要: 現場事務所など、ITインフラが整っていない場所でもすぐに確認できる
これらの手軽さから依然として紙での管理を続けている企業は少なくありません。しかしその手軽さの裏には、大きなデメリットが潜んでいます。
紙図面で管理する3つのデメリット
手軽さの代償として紙図面の管理は企業活動において多くの問題点を抱えています。特に以下の3つは生産性に直結する深刻な課題です。
①検索性・共有性の低さ:探すのに時間がかかる、属人化する
最大のデメリットは必要な図面をすぐに見つけ出せない「検索性の低さ」です。
「あの図面、どこにしまったかな…」「〇〇さんしか保管場所がわからない」といった状況は多くの現場で日常茶飯事ではないでしょうか。ある調査ではビジネスパーソンは1日のうち平均15分〜30分を探し物に費やしているというデータもあります。これが図面探しに当てはまると、年間で数十時間もの時間を浪費している計算になり深刻な人件費のロスです。
また保管ルールが曖昧だと管理が特定の担当者に依存する「属人化」を招きその担当者が不在の際には業務が完全にストップしてしまうリスクもあります。
②物理的な問題:保管スペースの圧迫、紛失・劣化・破損のリスク
紙の図面は保管すればするほど物理的なスペースを必要とします。特にA1サイズなどの大判図面は場所を取りオフィスの限られたスペースを圧迫し続けます。
さらに物理的な媒体である以上、紛失や盗難のリスクは常に付きまといます。誤って廃棄してしまったり持ち出し中に紛失したりすれば会社の重要資産を失うことになります。また紙は湿気や紫外線に弱く時間と共に劣化(黄ばみ、破れ)していくため、いざという時に文字や線が読めなくなっている可能性も否定できません。
③コストの問題:保管コスト、印刷コスト、探す時間という人件費
紙図面の管理には目に見えるコストと見えないコストが発生します。図面棚やキャビネットの購入費用、保管スペースの賃料といった「保管コスト」。図面を出力するための紙代やインク代、プリンターの維持費などの「印刷コスト」。
そして何より大きいのが、先述した「探す時間という見えないコスト(人件費)」です。これらのコストは図面が増え続ける限り永続的に会社に負担をかけ続けるのです。
【今すぐできる】紙図面の整理・保管・廃棄の具体的な方法
「データ化はすぐには難しい…」という方のために、まずは現状の紙図面を効率的に管理するための具体的な方法を解説します。ポイントは「誰でも」「すぐに」「同じように」できる仕組みを作ることです。
基本となる整理の3ステップ
まずは図面を整理し探しやすい状態にするための基本の3ステップをご紹介します。
Step1:要・不要の仕分け(最新版、旧版、参照用など)
最初にすべての図面を棚から出し「要るモノ」と「要らないモノ」に仕分けます。判断基準は以下のように設定するとスムーズです。
- 最新版(正): 現在進行中の案件や製造で必ず使用する図面。
- 旧版(副): 設計変更前の図面。基本は不要ですが変更経緯の確認用として一定期間保管する場合もあります。
- 参照用: 過去の類似案件など参考にすることがある図面
- 不要: 完全に役目を終え今後一切使わない図面
この仕分け作業は現場の担当者と設計担当者が一緒に進めるのが理想です。
Step2:ファイリングルールの策定(図番、案件名、日付など)
次に保管する図面をどのように分類しファイルに綴じるかのルールを決めます。重要なのは誰もが同じ基準でファイリングできるシンプルで明確なルールにすることです。
<ファイリングルールの例>
- 分類基準: 「案件番号」「製品カテゴリ」「図面番号」「作成年月日」など、自社で最も検索しやすい項目を軸にする。
- 並び順: 図面番号の昇順、日付の新しい順など並び順を統一する。
- ラベリング: ファイルの背表紙に記載する情報(例:案件番号-製品名)を統一し誰が見ても中身がわかるようにする。
Step3:保管場所のルール化と台帳作成(Excelテンプレートにも触れる)
最後にどこに何を保管するかという「保管場所のルール」を定めその情報を「図面管理台帳」にまとめます。
この台帳があるだけで検索性は劇的に向上します。Excelで簡単に作成できるので、ぜひ実践してみてください。
<Excel台帳の項目例>
- 図面番号
- 図面名
- 案件番号/案件名
- 作成日/改訂日
- 版数(バージョン)
- 保管場所(例:「B-3棚の上から2段目」など具体的に)
- 備考(関連図面番号など)
シンプルなExcelテンプレートを用意し共有フォルダに保存しておけば誰でも図面のありかを確認・更新できるようになります。
【サイズ別】かさばる図面の保管方法
図面のサイズによって最適な保管方法は異なります。特に管理が難しい大判図面の保管方法を中心にご紹介します。
A1/A2サイズ(大判図面):
- 図面棚(マップケース): 引き出し式で図面を平置きできるため折り目をつけずにきれいに保管できます。検索性は高いですが設置スペースが必要です。
- 図面キャビネット: 図面を立てて保管するタイプ。マップケースより省スペースですが図面の出し入れに少し手間がかかる場合があります。
- 吊り下げ式ファイル(アポロケースなど): 図面に穴を開けずに挟み込み吊り下げて保管します。省スペースでめくりながら探せるのがメリットです。
A3/A4サイズ:
- リングファイル/パイプ式ファイル: 最も一般的な方法。案件ごとや製品カテゴリごとにまとめ背表紙にラベルを貼って本棚に立てて保管します。
- 個別フォルダー+ボックスファイル: フォルダーごとに図面を分類しボックスファイルに入れて管理します。出し入れが容易で案件単位での持ち運びにも便利です。
知らないと危険!紙図面の正しい廃棄方法とは?
整理のステップで「不要」と判断された図面ですが安易にゴミ箱に捨ててはいけません。製品の設計情報が記載された図面は企業の重要な「機密情報」です。情報漏洩を防ぐため適切な方法で廃棄する必要があります。
- 溶解処理: 最も安全な方法です。専門の廃棄物処理業者が図面を箱ごと未開封のまま溶解炉で溶かしてしまうため情報が復元される心配がありません。機密保持契約を結び「溶解証明書」を発行してくれる業者を選びましょう。
- シュレッダー処理: 自社で処理する場合は復元が困難な「マイクロカット」など、裁断サイズの細かい業務用シュレッダーを使用しましょう。ただし大量の図面を処理するには時間と手間がかかります。
一般ごみとして廃棄したり裁断の甘いシュレッダーを使ったりすると第三者に情報を読み取られ思わぬトラブルに発展するリスクがあります。必ずルールを定めて安全に廃棄してください。
みんなはどうしてる?他社の図面整理・保管事例
とある中小製造業A社では属人化していた図面管理に悩んでいました。そこで、ベテラン社員と若手社員がチームを組み全図面の洗い出しを実施。「製品カテゴリごと」に色分けしたファイルで管理しExcelの管理台帳を作成しました。結果、以前は15分以上かかっていた図面探しが新人でも3分以内に見つけられるようになり問い合わせ対応のストレスも大幅に軽減されたそうです。
紙図面管理の課題を根本から解決する「データ化」という選択肢
ここまでは現状の紙図面を整理する方法を解説しましたが、これらは対症療法に過ぎません。課題を根本から解決し生産性を高めるには「図面のデータ化」が最も有効な手段です。
なぜ今、図面のデータ化が必要なのか?
社会全体でペーパーレス化やDX(デジタルトランスフォーメーション)が進む中、図面管理もデジタル化への移行が求められています。図面をデータ化することでこれまで述べてきた紙管理のデメリット(検索性、共有、保管スペース、劣化、コスト)をすべて解消できます。
- 検索性が劇的に向上: ファイル名や図面内の文字で一瞬で検索可能
- 共有が容易: サーバーやクラウドに保存すればいつでも誰でもアクセス可能
- 保管スペースが不要: 物理的な場所を取らずオフィスを有効活用
- 劣化しない: データなので経年劣化の心配がなくバックアップも容易
- コスト削減: 保管コスト、印刷コスト、そして探す人件費を大幅に削減
データ化はもはや一部の先進企業だけのものではなくすべての企業が取り組むべき経営課題となっています。
図面をデータ化する具体的な3ステップ
Step1:スキャニングとPDF化
まず紙の図面をスキャナーで読み取り電子データ(一般的にはPDF形式)に変換します。
- 自社で行う場合: A3サイズまでなら複合機で対応できますがA1などの大判図面には専用の大判スキャナーが必要です。初期投資はかかりますが少量ずつ自社のペースで進められます。
- 専門業者に依頼する場合: 大量の図面や大判図面がある場合に有効です。高品質なスキャニングが期待できファイル名の入力なども代行してくれるサービスもあります。コストはかかりますが自社のリソースを割かずに済みます。
Step2:ファイル名のルール統一
スキャンしただけのデータはただの画像の集まりです。検索性を高めるために統一されたファイル名のルールを策定することが極めて重要です。
<ファイル命名規則の例>
[案件番号]_[図面名]_[作成日]_[版数].pdf
例: P202507-01_本体組立図_20250731_v3.pdf
このようにルール化することで誰が見てもファイルの内容が推測でき検索も容易になります。
Step3:管理方法の決定
データ化した図面をどのように保管・管理するかを決定します。
- フォルダ管理: 最も手軽な方法。サーバー上に「案件ごと」「製品ごと」などのルールでフォルダを作成し格納します。ただしファイルが増えると検索が遅くなったり誤って上書きや削除をしてしまったりするリスクがあります。
- Excel管理: 先ほどの管理台帳にデータファイルの保管場所(ハイパーリンク)を追記する方法。検索性は向上しますが同時編集が難しいデータ量が増えると動作が重くなるなどのデメリットがあります。
- 図面管理システム: 図面管理に特化した専用システム。高度な検索機能、厳密なバージョン管理、アクセス権設定などフォルダ管理やExcel管理の弱点をすべてカバーできます。
図面管理システムの選び方【無料と有料の違い】
図面管理を本格的に行うなら専用システムの導入が最適です。無料のツール(オンラインストレージなど)でも代用は可能ですがビジネスで利用するには機能不足な面が多くあります。
無料ツールは手軽ですが図面の版数(バージョン)管理が難しく「どれが最新版かわからない」という事態に陥りがちです。またセキュリティ面での不安やサポートが受けられない点もデメリットです。
一方、有料の図面管理システムはこれらの課題を解決するために設計されています。
- 高度な検索機能: 図番や製品名だけでなく図面内の文字列(OCR機能)でも検索可能
- 厳密な版数管理: 常に最新版がわかる仕組みで古い図面を誤って使用するミスを防止
- セキュリティ: ユーザーごとにアクセス権限を設定でき不正な閲覧や持ち出しを防止
- ワークフロー機能: 図面の承認プロセスをシステム化し業務を効率化
長期的な視点で見れば初期投資を払ってでも信頼性の高い有料システムを導入するメリットは非常に大きいと言えます。
図面管理の最適化で生産性を向上させる方法
数ある図面管理システムの中でも製造業の現場課題を熟知して開発されたツールを選ぶことが成功の鍵です。
【結論】最適な図面管理は「SellBOT」で実現
数ある図面管理システムの中でも製造業が抱える「探せない」「見積りに時間がかかる」「ノウハウが属人化する」といった根深い課題を独自のAI技術で根本から解決するために開発されたのが次世代の図面管理システム「SellBOT」です。
これまで解説してきた紙やフォルダでの管理課題をSellBOTはどのように解決するのか。その核心となる機能は単なるデータ検索ではありません。
図面が検索キーワードになる「AI類似図面検索」
SellBOTの最大の特徴は図面そのものをAIが解析し過去の類似した図面を瞬時に探し出す「AI類似図面検索」機能です。
使い方は驚くほどシンプル。新しい図面データをアップロードするだけ。するとAIが形状を読み取りデータベースの中から「似ている図面」を自動でリストアップします。品番やファイル名が分からなくても「この図面に似た過去の案件は?」というまるでベテラン社員のような感覚的な探し方を誰でも実現できるのです。
さらに、見つかった類似図面と今回検索した図面の「どこが違うのか」をAIが自動で色付けしてハイライト表示する「AI差分表示」機能も搭載。これにより変更点の確認や見積もりの精度が劇的に向上し確認作業の負荷を大幅に削減します。いままで担当者が数十分かけて行っていた検索と確認作業がわずか1分で完了します。
SellBOTがもたらす、具体的な導入効果
実際にSellBOTを導入した企業では、劇的な業務改善が実現しています。
見積もり・検索時間を大幅に削減
- 個人の記憶を頼りに図面を探していた株式会社ファム様では、図面検索時間を90%削減。営業提案のスピードと質が向上しました。
- 社長自らが見積もり作業に忙殺されていた株式会社森産業様では、見積もり工数を75%削減し社長が本来の経営業務に専念できる環境を構築しました。
ベテランへの依存から脱却し若手が即戦力に
- 若手社員の教育に課題を抱えていた株式会社アイジェクト様では、SellBOTの導入により「若手が即戦力化」。ベテランのノウハウをAIが引き継ぎ誰でも精度の高い業務が可能になりました。
- 見積もりが属人化していた京都樹脂精工株式会社様では、「誰でも、どこでも、ベテラン並みの見積もり」を作成できる仕組みを確立しました。
このように、SellBOTは単なるデータ保管庫ではありません。図面という会社の重要資産とそこに眠るベテランのノウハウを「見える化」し、全社員が活用できる形に変えることで業務プロセス全体を効率化する経営改革ツールなのです。
まとめ
本記事では、かさばる紙図面の整理方法から課題を根本解決するデータ化そして最適な図面管理システム「SellBOT」までを解説しました。
- 現状の課題解決: まずは「仕分け」「ルール化」「台帳作成」の3ステップで、現状の紙図面を整理しましょう。これだけでも業務効率は改善されます。
- 根本的な課題解決: しかし、紙で管理し続ける限り保管スペースや検索性の問題はなくなりません。長期的な視点に立ち図面の「データ化」を進めることが生産性向上の鍵です。
- 未来への投資: データ化した図面を最大限に活用するには「SellBOT」のような高性能な図面管理システムの導入が最適解です。図面を探す時間をなくし全社員が本来の創造的な業務に集中できる環境を構築できます。
図面管理の改善は後回しにされがちな業務かもしれません。しかしここに着手することこそがDX時代の製造業が競争力を維持し成長し続けるための重要な一歩です。
まずは貴社の図面管理の課題を整理し何から始めるべきか考えてみませんか?
「SellBOT」がどのように貴社の課題を解決できるか具体的な導入事例や機能を紹介しております。
「Q&A」紙図面の整理に関するよくある質問
Q. A1サイズの図面を保管するにはどうしたらいいですか?
A. A1サイズのような大判図面は平置きできる図面棚(マップケース)や、立てて保管する図面キャビネット、吊り下げ式のファイルなどがおすすめです。折り目をつけずに保管でき劣化を防ぎます。詳しくは本文の「【サイズ別】かさばる図面の保管方法」をご覧ください。
Q. 紙図面の廃棄方法は?
A. 図面は機密情報を含むため一般的な書類と同様に廃棄してはいけません。情報が復元できないよう専門業者による「溶解処理」を依頼するかマイクロカットなど裁断が細かい大型の業務用シュレッダーで処理するのが安全です。詳細は「知らないと危険!紙図面の正しい廃棄方法とは?」で解説しています。
Q. そもそも図面管理の問題点は何ですか?
A. 主な問題点は「探すのに時間がかかる(検索性)」「担当者しか場所がわからない(属人化)」「保管スペースを圧迫する(物理的問題)」「紛失・劣化のリスクがある」など多岐にわたります。これらは見えないコストとして企業の生産性を低下させる要因となります。詳しくは「紙図面で管理する3つの大きなデメリット」で詳しく解説しています。